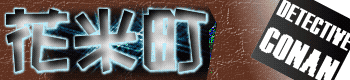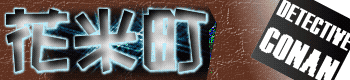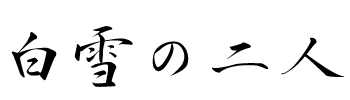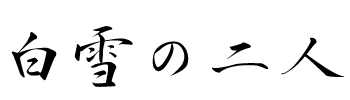
――何かしら……あれ?
阿笠邸の前まで帰った時、哀は隣の家の門前に落ちている物に目を留めた。
それに近付いて拾い上げ、哀はそれが何なのかわかった。
「彼女のだわ……」
それは、以前、コナンが蘭の為に買っていたストラップだった。
きっと、掃除に来た時にでも落としてしまったのだろう。
――届けなくちゃ……
哀は、ランドセルを置きに阿笠邸の扉を開けた。
「おぉ、哀君。おかえり」
「ただいま」
哀は入ってすぐの机の上にランドセルを置くと、玄関へ引き返した。
ストラップはコートのポケットの中だ。
「雪が降っておるのに、今日も新一君達と遊ぶのか?」
「まぁ、そんな所……」
「じゃあ、帰った時にはいないかも知れないのぉ。
今日は学会があるんじゃ。鍵はポストの中に入れておくからの」
哀は雪の降る外へ出た。コートを着ているとは言え、雪が降っているだけあってかなり寒い。
哀はポケットの中のストラップを確認し、唇を噛んだ。
――わかってるわよ、私の罪は消えない事ぐらい……
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
――あ……
哀はハッとして立ち止まった。
いつの間にか、毛利探偵事務所とは違う方向へ来ていたのだ。
前方には東都タワーが見えている。空も、もう紅い。
「何してるのかしら、私……」
届けなくてはいけない。わかっている。わかっているのに。
――気が進まない……
あの時、拾わなければ。
あの時、近付かなければ。
あの時、工藤家の方を見なければ。
そう思っても、どうしようも無い。
あの時工藤家の方へ視線が行ったのは、認めたくは無いが、恐らく……。
そして、今、拾ってしまったストラップを届けるのを戸惑っているのも、同じ理由。
「……」
立ち止まっている哀の肩に、白い雪が静かに降り積もる。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「哀ちゃん?」
その声に、哀はハッとして顔を上げた。
最も会いたくない人に会ってしまった。
蘭だ。
「どうしたの?こんな所で……風邪ひくよ?」
蘭は優しく微笑み、哀の肩に積もった雪を払い落とす。
その手には、手袋がはめられている。恐らくこれも、彼からの……。
哀は表情を見せまいと俯くと、ポケットの中の物を取り出した。
「これ……隣の家の前に落ちてたわ」
蘭が、ストラップを受け取ると、哀はすぐに手を下ろした。
手袋の無い手を、さっきまでストラップが入っていたコートのポケットへ隠すように入れる。
「ありがとう!そっか、新一の家の前に落ちてたのね……。
探したけど、見つからなくって。本当にありがとう」
「じゃあ、渡したから……」
哀が背を向けると、蘭が呼び止めた。
「待って!ねぇ、お礼って言ったらなんだけど、夕飯、一緒に食べない?
夕食の材料買った後なのに、お父さん、ちょっと用事ができちゃって……」
用事というのは恐らく麻雀の事だろう。見ると、蘭は片手にパンパンの買い物袋を提げている。
「でも……博士もいるから……」
「え?でもコナン君、博士は今日、学会でいないって言ってたわよ?
家に行ったら、扉に張り紙してあったって」
「……」
「遠慮しなくていいわよ。ね?ホラ、行こう♪」
蘭は哀の手を取ると、歩き出した。哀は仕方なく、歩調を合わせた。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
哀と、蘭と、コナン。奇妙なメンバーでの、奇妙な空気の食事。
場を盛り上げようとしてか、それともその空気に気づかずか、蘭が学校での出来事を二人に明るく話す。
そして時々、コナンが口を挟む。哀は黙々と箸を進める。
「コナン君、またご飯粒付けて……」
蘭がハンカチを取り出し、コナンの口元を拭く。
哀は、皮肉っぽくクスリと笑った。
――高校生にもなって……
哀に冷たく笑われ、コナンは決まり悪そうにする。
「『また』って事は、いつもなのね」
哀はあきれ返ったように言う。
これは強がりだ。本当は、平気でなんていられない。
コナンと蘭が一緒にいるのを見ると、いつも心が悲鳴をあげそうになる。
でも、決意したから。
もう、逃げない、と。
この痛む心からも、組織からも。
勇気を出して。
――勇気……身を奮い立たせる、正義の言葉……
そう言ったのは、彼女だ。
――皮肉よね……。彼女の言葉で決心するなんて
だが、もしかしたら、彼女が言ったからこそ、決心できたのかもしれない。
「ご馳走様」
哀は手を合わせると、食器を流しに運んだ。
「あ。哀ちゃん、ありがとう。そこに置いといていいわよ」
食器を洗う為にスポンジを取ろうと背伸びをする哀に、蘭は言った。
「そう。じゃ……ご馳走様でした」
哀は部屋の隅へ行き、コートを着る。
「えっ。待って、哀ちゃん。送っていくわよ。もう、遅いし」
「平気よ。近いもの」
哀はコートのボタンを留めると、扉を開けた。
「ありがとうございました。じゃ、さよなら」
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
雪はまだ、降っていた。
黒い空から、白い雪。哀の肩に降り積もる。
「……」
哀は唇を噛むと、阿笠邸に向かって足早に歩いて行った。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「蘭姉ちゃん。これ、学校のプリント……あれ?」
扉を開け、コナンは首を傾げた。蘭がいない。
自室だろうか……?そう思って蘭の部屋の前に行き、ノックをするが、やはり応答無し。
「どこへ行ったんだ……?」
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
「哀ちゃん。待って!」
背後から声をかけられ、哀は振り返った。蘭が走ってくる。
「送っていくよ。いくら近いって言ったって、小学生の女の子が夜道を一人歩いてるなんて、危ないもの」
「あなただって、帰り、一人になるわよ」
「私は大丈夫。空手があるから☆」
「……」
雪の降る夜道を、二人は歩く。
「雪……キレイね……」
蘭が、空を見上げ、呟く。哀は、俯いた。
「雪なんて嫌いよ……雪の白さは、黒い者を責め立てる……
黒は、この場にあってはいけないってね……」
蘭はきょとんとした表情だ。
蘭が口を開いて何かを言おうとした時、声がした。
「蘭姉ちゃーん!」
コナンが、蘭の横に駆け寄る。
「やっぱり、灰原を送ってたんだね」
「だって、一人じゃ危ないでしょ?」
そう言って、蘭は微笑む。
白い彼女。冷たく黒い自分とは、正反対で。
白い世界にいる彼が、彼女に惹かれるのも無理は無い。
自分のような黒い人間は、この場では場違いで。
哀は、楽しそうに話す二人を、寂しげに見つめた。
◆ ◆ ◆ ◆ ◆
間もなく、阿笠邸に着いた。
「じゃあ……一応、お礼を言っておくわ。送ってくれて、ありがとう。
ま、頼んでもいないけどね……」
「おまえ、まじで可愛くねぇな……」
「コナン君、女の子にそんな事言っちゃダメよ。じゃあね、哀ちゃん」
哀は二人に背を向けた。ポストに入っていた鍵を鍵穴に挿した時、蘭が思い出したように言った。
「あ。そう、そう。哀ちゃん」
哀はゆっくりと振り返る。蘭は、にっこりと笑った。
「哀ちゃんは、黒くなんか無いよ。ホラ、"朱に交われば紅くなる"って言うでしょ?」
「……」
「?」
コナンが、何の話かわからず、きょとんとする。
「じゃあね、哀ちゃん。行こう、コナン君」
二人は手を繋ぎ、帰っていった。
哀は、さっきの蘭の言葉を心の中で繰り返す。
――じゃあ、名前の通り、灰色って所かしら?だから、独りなのかもね……。
白の世界にも、黒の世界にも、属す事ができないから
――でも、黒から灰色になれたなら、いつかは彼と同じ世界に溶け込めるようになるかもしれない……
〈「白雪の二人」終わり〉